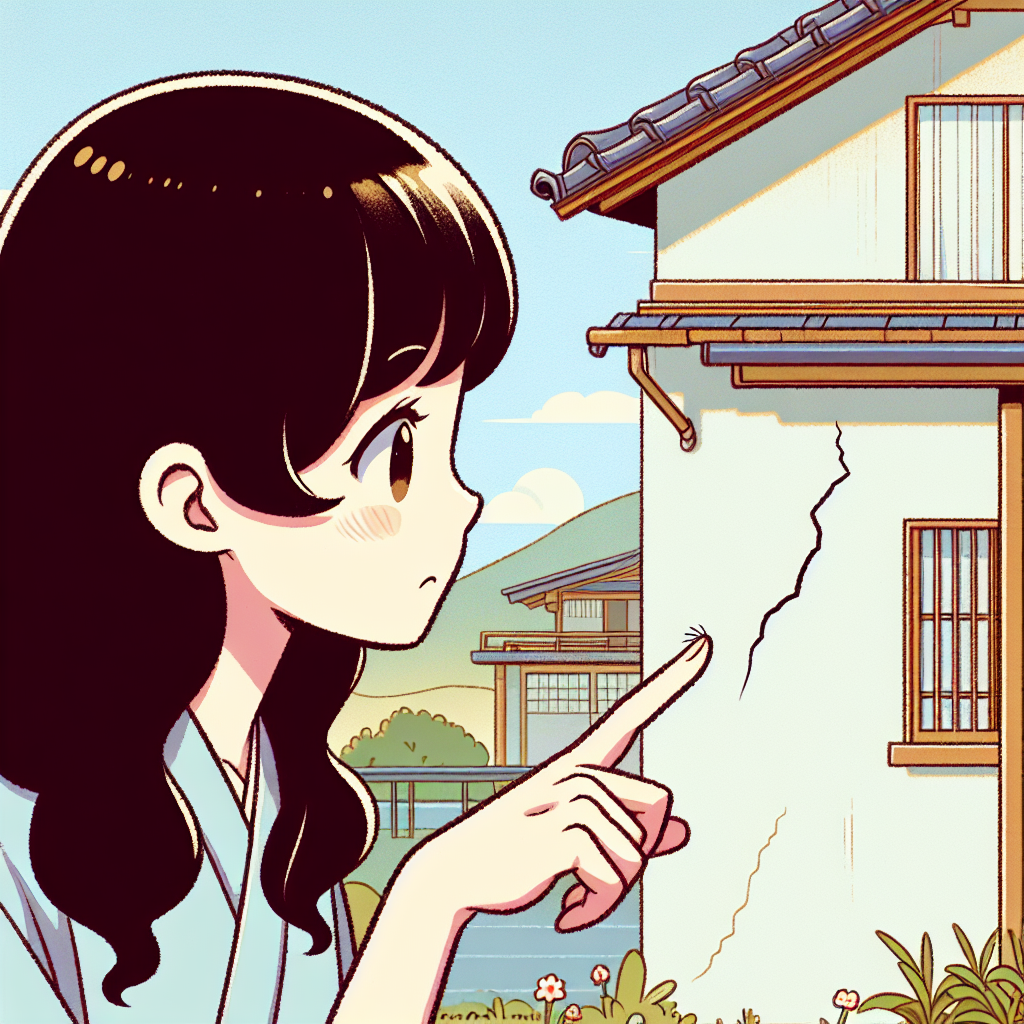「3回塗り」は当たり前?塗料の性能を100%引き出す塗装工程の重要性
「外壁塗装は3回塗りが基本って聞くけど、どうして?」
「2回塗りじゃダメなの?回数を減らせば安くなるんじゃ…」
外壁塗装の見積もりや説明の中で、必ずと言っていいほど出てくる「3回塗り」という言葉。これは、塗料が持つ性能を100%引き出し、建物を長期間保護するために欠かせない、非常に重要な基本原則です。
この記事では、なぜ3回塗りが必要なのか、それぞれの工程が持つ役割と、もし工程を省かれてしまった場合に起こるリスクについて、詳しく解説します。
なぜ「3回塗り」が必要なのか?
塗料メーカーが製品を開発する際、その塗料が最も効果を発揮する「最適な塗り方」として、塗り回数や乾燥時間などを定めています。ほとんどの家庭用塗料は、この「3回塗り」を前提として、その耐久性や防水性が設計されています。
それぞれの塗り工程には、化粧に例えると分かりやすい、明確な役割分担があります。
1回目:下塗り(化粧下地)
役割:外壁材と仕上げ塗料を密着させる接着剤
高圧洗浄や下地処理でキレイになった外壁に、最初に塗るのが「下塗り」です。
- 密着性の向上: 仕上げとなる塗料(中塗り・上塗り)が、壁から剥がれにくくなるように、強力な接着剤の役割を果たします。
- 下地の補強: 傷んだ外壁材に塗料が吸い込まれすぎるのを防ぎ、仕上がりの色ムラをなくします。
- 特殊機能の付与: サビ止め効果のある下塗り材や、小さなひび割れを埋める効果のある下塗り材(フィラー)など、下地の状態に合わせた機能を持たせることもできます。
この下塗り工程を省くと、どんなに高価な仕上げ塗料を使っても、数年でペリペリと剥がれてきてしまいます。
2回目:中塗り(ファンデーション)
役割:塗膜に厚みを持たせ、色と機能を付ける
下塗りが完了し、十分に乾燥させた後に塗るのが「中塗り」です。ここからが、実際に壁の色を付けていく工程になります。
- 塗膜の厚み確保: 塗料の防水性や耐久性は、メーカーが定めた「規定の厚み(塗布量)」が確保されて初めて発揮されます。中塗りは、この厚みを付けるための重要な工程です。
- 色ムラの防止: 上塗りの前に一度同じ色を塗っておくことで、最終的な仕上がりの色ムラを防ぎ、発色を良くします。
3回目:上塗り(仕上げ・コーティング)
役割:美観と保護機能の最終仕上げ
中塗りが乾燥した後、同じ塗料をもう一度塗り重ねるのが「上塗り」です。仕上げの工程となります。
- 塗りムラの最終補正: 中塗りだけでは、どうしてもわずかな塗りムラや塗り残しが発生します。上塗りをすることで、それらを完全にカバーし、美しく均一な仕上がりにします。
- 塗膜の厚みを完璧にする: 中塗りと合わせて、規定の塗膜の厚みを確保し、塗料が持つ耐久性、防水性、防カビ性などの性能を最大限に引き出します。
もし「2回塗り」で済ませたら…?
もし悪質な業者が利益を出すために、下塗りや中塗りの工程を省き、2回塗りや1回塗りで済ませてしまったらどうなるでしょうか。
- 数年で塗膜が剥がれる: 下塗りが不十分だと、密着性が弱く、すぐに塗装が剥がれてきます。
- 色ムラや透け: 中塗りを省くと、下地の色が透けて見えたり、色がまだらになったりします。
- 期待された耐用年数を大幅に下回る: 規定の塗膜の厚みがなければ、塗料本来の耐久性は発揮されません。15年持つはずの塗料が、5年で劣化してしまうこともあります。
結果的に、すぐに再塗装が必要になり、「安物買いの銭失い」となってしまうのです。
まとめ:3回塗りは、高品質の証
外壁塗装における「3回塗り」は、単なる慣習ではありません。それは、塗料の性能を最大限に引き出し、あなたの大切な家を長期間にわたって守るための、科学的根拠に基づいた絶対的なルールです。
見積書に「下塗り・中塗り・上塗り」の3つの工程がきちんと明記されているか、そして、実際の作業現場でもその工程が守られているか(作業報告書などで確認)をチェックすることが、手抜き工事を防ぎ、満足のいく塗装を実現するための鍵となります。