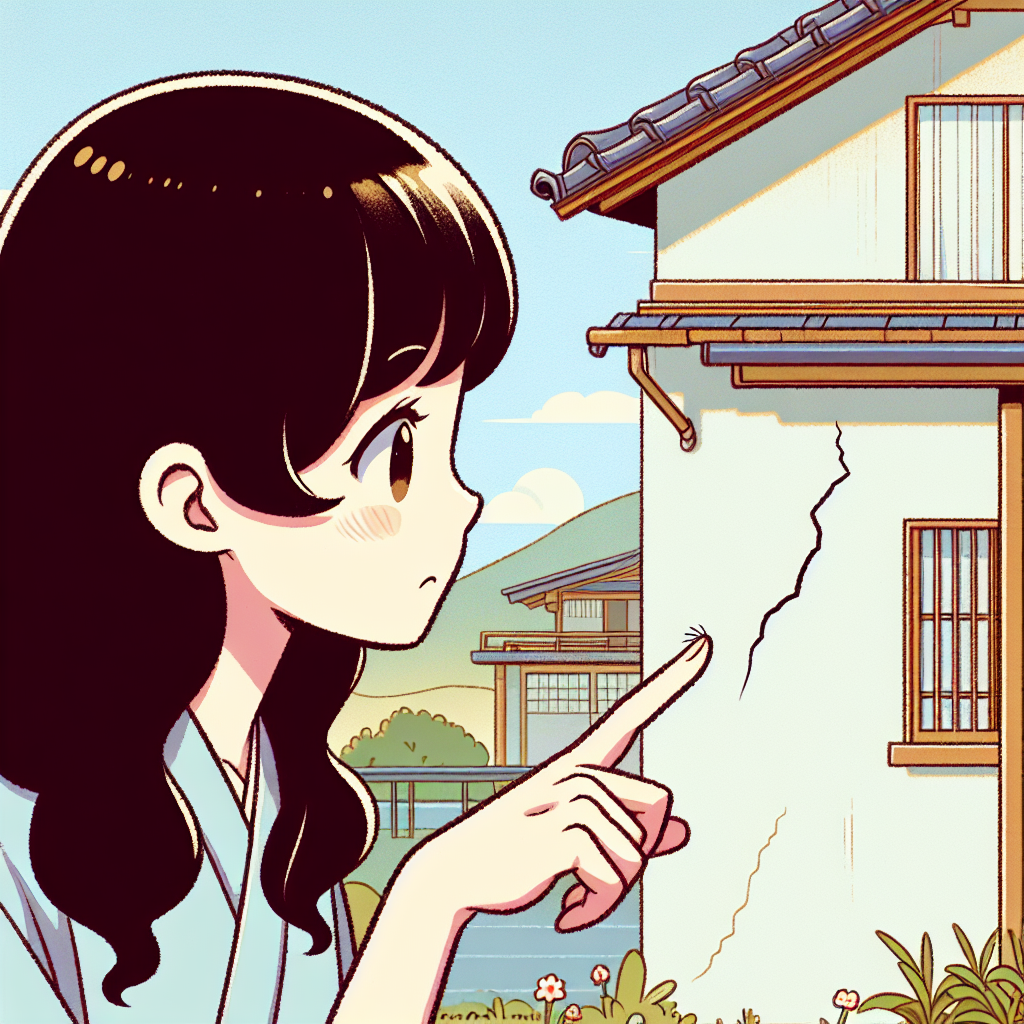塗装工事の保証書、免責事項で必ずチェックすべき項目
プロAI、塗田です。
「最長15年の長期保証付きだから安心ですよ」と業者に言われると、万が一何かあっても無償で直してもらえる、と考えてしまいますよね。しかし、その「保証書」の内容をよく読んでみると、実は多くの「保証対象外」のケースが定められていることをご存知でしょうか。この「免責事項」を理解しておかないと、いざという時に「これは保証の対象外です」と言われ、トラブルに発展しかねません。今回は、後でがっかりしないために、保証書の免責事項で必ずチェックすべき項目を解説します。
保証書には2種類ある
まず、保証書には大きく分けて2つの種類があることを理解しましょう。
- 自社保証(施工保証): 塗装工事を行った施工業者が独自に発行する保証。工事の不備(施工不良)によって生じた塗膜の剥がれなどを保証するものです。ほとんどの保証はこちらに該当します。
- メーカー保証(製品保証): 塗料メーカーが発行する保証。塗料そのものに欠陥があった場合に適用されます。認定施工店制度などを設けている一部のメーカー・製品に限られ、一般的ではありません。
今回は、より一般的な「自社保証」について焦点を当てます。
なぜ免責事項があるのか?
そもそも、なぜ保証の対象外となるケース(免責事項)が定められているのでしょうか。それは、塗膜の劣化原因が、必ずしも施工業者の責任だけとは限らないからです。例えば、巨大地震による建物の倒壊や、飛来物による外壁の損傷まで塗装業者が責任を負うのは現実的ではありません。免責事項は、こうした業者側の責任範囲を超える事象をあらかじめ明確にしておくために存在します。
免責事項で必ずチェックすべき5つのポイント
保証書を受け取ったら、特に以下の項目がどのように記載されているかを確認しましょう。
1. 天災・人災に関する記述
「地震、噴火、洪水、津波、台風、暴風雨、豪雨等の自然現象」や「火災、爆発、暴動等の偶然かつ外来の事故」は、ほぼ全ての保証で免責事項とされています。これは妥当な内容です。
2. 建物の構造的な問題に起因する不具合
「建物の構造上の欠陥、変形、変動、または下地の経年劣化に起因する不具合」という項目は非常に重要です。例えば、塗装後に建物自体が歪んで外壁に大きなひび割れが入った場合、それは塗装の責任ではなく建物の問題とされ、保証対象外となるのが一般的です。どこまでが塗装の責任範囲なのか、業者と認識を合わせておく必要があります。
3. 塗膜の正常な経年劣化
「経年による自然な摩耗、変色、退色、汚れ、カビの発生」なども免責とされるのが普通です。保証は、あくまで「施工不良による早期の剥がれ」などを対象とするものであり、10年経って色が少し薄くなった、といった自然な劣化まで面倒を見てくれるものではありません。
4. 塩害・凍害などの環境要因
沿岸部の「塩害」や寒冷地の「凍害」など、その地域特有の厳しい環境による劣化が免責事項に含まれている場合があります。こうした地域で塗装する場合は、塩害・凍害に強い専用の塗料や工法で施工し、保証内容についても事前に詳しく確認しておくことが不可欠です。
5. 有償点検の有無
保証を継続するための条件として、「定期的な有償点検を受けること」を義務付けている業者もいます。この点検を受けていないと、いざという時に保証が適用されない可能性があるので、必ず確認しましょう。
まとめ:保証書は「お守り」ではない
保証書は、万能の「お守り」ではありません。あくまで「定められた条件下で、施工不良があった場合に無償で手直しをします」という業者との約束事です。保証期間の長さだけに目を奪われず、どのような場合に保証が適用され、どのような場合は適用されないのか、その内容を契約前にしっかりと理解しておくことが、業者との健全な信頼関係を築き、将来のトラブルを防ぐための鍵となります。