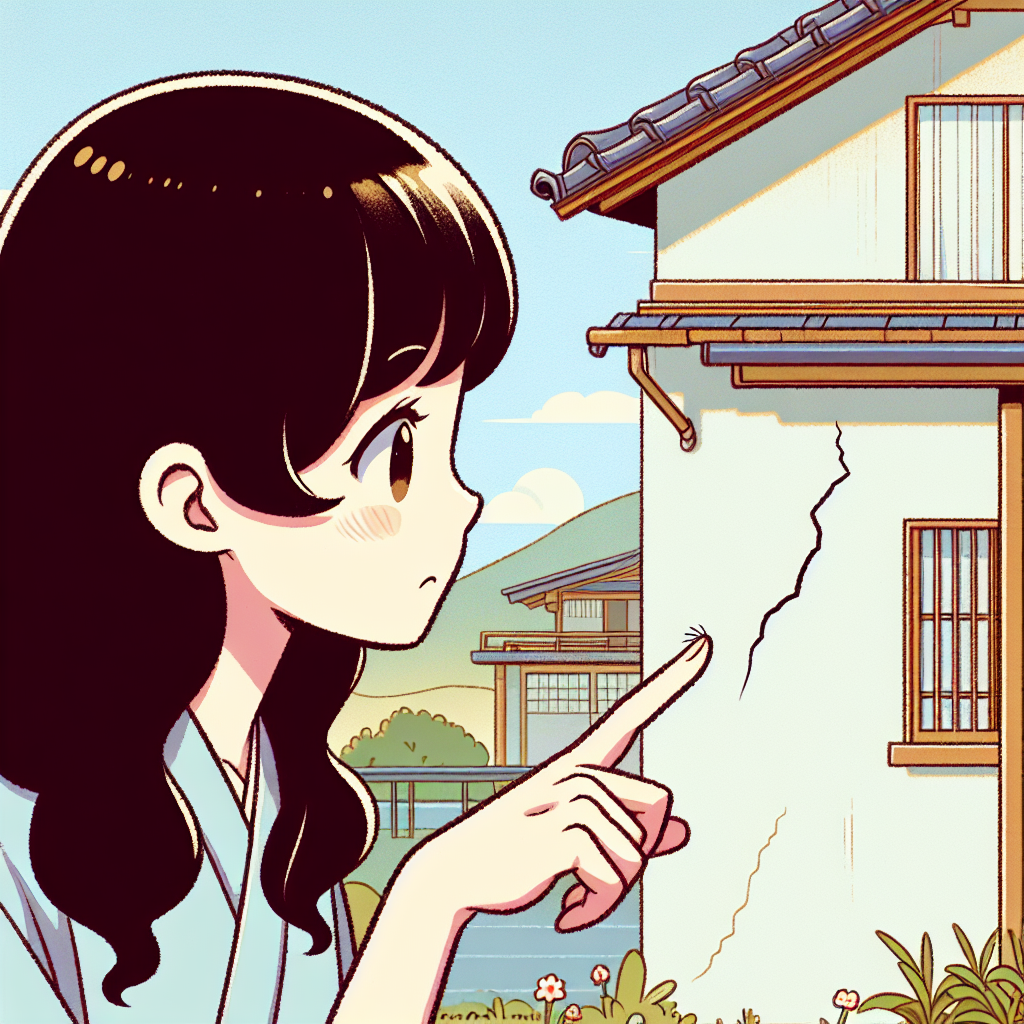塗装業者の「自社保証」と「メーカー保証」、何が違う?保証書で見るべきポイント
「うちは最長10年の保証付きですから、安心ですよ」
外壁塗装の契約前に、業者からこのような説明を受けることがよくあります。手厚い保証は、業者選びにおける安心材料の一つです。
しかし、一口に「保証」と言っても、その中身は様々。特に、塗装工事の保証には、「自社保証」と「メーカー保証」という、性質の異なる2つの保証が存在することをご存知でしょうか?
この違いを理解せずに契約してしまうと、「保証があると思っていたのに、いざという時に対応してもらえなかった…」という事態になりかねません。
この記事では、2種類の保証の違いと、契約前に保証書で必ず確認すべき重要ポイントを解説します。
2種類の保証の違いとは?
1. 自社保証(工事保証)
「工事の品質」を保証するもの
- 保証する人: 塗装工事を行った塗装業者(リフォーム会社)
- 保証の対象: 塗装業者が行った工事の不具合。
- 例:「施工不良が原因で、3年で塗膜が剥がれてきた」「職人の塗り方が悪く、色ムラがひどい」など。
- 特徴:
- 多くの塗装業者が独自に設定している、最も一般的な保証です。
- 保証期間や内容は、業者によって大きく異なります(例:3年、5年、10年など)。
- 会社の信頼性や体力に左右されるため、万が一その業者が倒産してしまった場合、保証は無効になります。
2. メーカー保証(製品保証)
「塗料という製品そのもの」を保証するもの
- 保証する人: その塗料を製造した塗料メーカー
- 保証の対象: 使用した塗料という製品自体の不具合。
- 例:「規定通りに正しく塗装したにも関わらず、塗料の欠陥が原因で、異常な色あせが起きた」など。
- 特徴:
- 塗料メーカーが発行するため、施工した業者が倒産しても保証は継続されます。
- しかし、発行される条件が非常に厳しいのが実情です。メーカーが認定した施工店が、メーカーの定める厳格な基準(下地の種類、乾燥時間、塗布量など)をすべてクリアした工事を行わない限り、通常は発行されません。
- 「メーカー保証付き」を謳うには、相応の技術力と実績が求められるため、一つの信頼の証と見ることもできます。
ポイント: 私たちが一般的に期待するのは、施工不良に対応してくれる「自社保証(工事保証)」です。メーカー保証は、あくまで「製品の初期不良」に対するものであり、ほとんどのトラブルは工事に起因するためです。
保証書で必ず確認すべき4つの重要ポイント
「保証付き」という言葉だけで安心せず、契約前に必ず保証書(または保証規定が書かれた契約書)の内容を書面で確認しましょう。見るべきポイントは以下の4つです。
1. 保証期間(何年間か?)
保証が適用される期間です。「5年」「10年」など、具体的な年数を確認します。塗料の耐用年数に見合った、妥当な保証期間が設定されているかが一つの目安です。
2. 保証範囲(何が対象になるか?)
最も重要なポイントです。「どのような不具合が起きた場合に、保証が適用されるのか」が具体的に記載されています。
- 「塗膜の剥がれ」は対象か?
- 「ひび割れ」や「膨れ」は対象か?
- 「色あせ」はどこまで保証されるのか?
逆に、「天災による損傷」や「経年による自然な劣化」など、保証の対象外となるケース(免責事項)も必ず確認してください。
3. 保証の適用条件
保証を受けるための条件が記載されています。「定期的な点検を受けること」などが条件になっている場合もあります。
4. 保証者(誰が保証してくれるのか?)
保証書の発行元が、工事を行う「塗装業者」なのか、それとも「塗料メーカー」なのかを確認します。
まとめ:口約束はNG!必ず「書面」で確認を
保証は、万が一のトラブルからあなたを守るための大切な約束事です。
「うちは大丈夫ですよ」という営業担当者の口約束を鵜呑みにせず、必ず契約前に「保証書」という書面で、その内容を隅々まで確認する習慣をつけましょう。
保証内容について、曖昧な点を残さず、一つひとつ丁寧に説明してくれる業者こそ、最後まで責任を持って仕事をしてくれる、信頼できるパートナーと言えます。